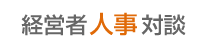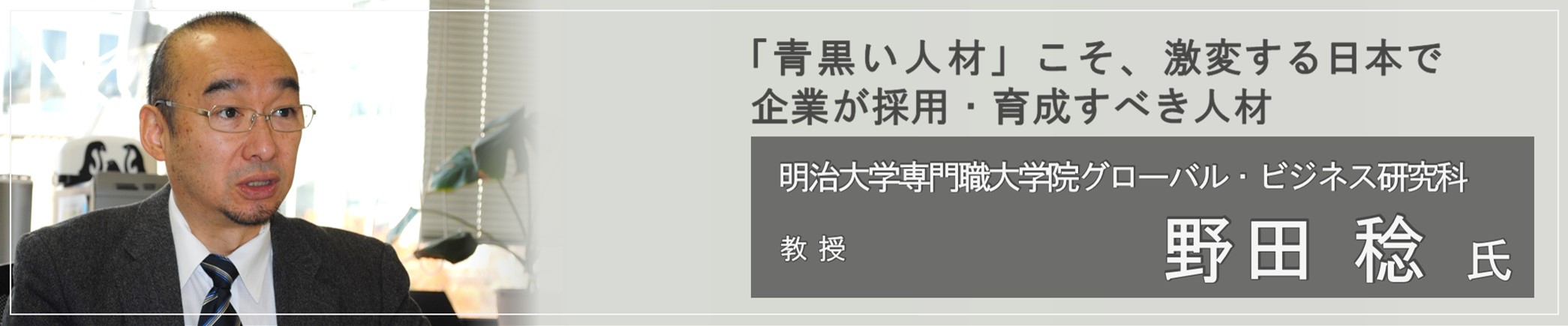明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科 教授 として、また、リクルート社のワークス研究所特任研究顧問として、人材育成の最先端を研究なさっている野田 稔 氏に、これからの日本において採用・育成すべき人物像について伺いました。
日本企業の経営戦略の変化と人材育成の関係とは
樋口:
戦後から日本企業を取り巻く環境が大きく変わり、それに伴い企業の経営・人事戦略も大きく変わったと思います。野田先生は、その変遷をどのようにご覧になりますか。
野田:
おっしゃるとおり、企業の目指す姿は時代とともに変遷してきたと思います。
日本の経営は三つの世代でかわっていきました。まず1945年から1975年の30年間、オイルショックくらいまでの時代です。戦後のこの時期は人口が急増し、物資が不足でモノを大量に供給することが求められた時代。これが第一世代で、日本企業はこの時期の時代の要請に非常にうまく適応したと思っています。
その後人口が微増に転じ、国内マーケットが成熟化し、世界に目を向けた時代。第二世代になり、企業はニーズの多様化に応えようともがき苦しんでいたように思います。
今後は、人口が減少に転じ、社会全体が縮小する第三世代が到来します。これからは、これまで公のセクターが担ってきた社会課題に対し、イノベーションの力で解決を図る企業が増えていかなければならない時代ですね。

こうした時代の変化に伴い、企業の人事・育成戦略はどのように変わるでしょうか。
画一性が求められた第一世代では、年功序列・終身雇用をベースとする人事が行われました。「明日を夢見て今日は我慢」が人事のキーワードでした。これにより、目先のコストを抑制しつつモチベーションを維持することができました。
一方多様性が重視されてきた第二世代では各々の専門性が非常に重要で、スペシャリストを養成する人事が行われてきたと解釈しています。
第三世代に突入する今後、価値創造できる人材が求められる上で、企業や人事はより一層変化に対応していく必要があります。専門性は引き続き必要ですが、創造性を発揮するためにはその上で幅広い知識や視点が必要となり、その要素を積み上げなければならないということです。
問題は第二世代のスペシャリスト人材が第三世代に移行して有効に機能するかどうかです。多くのスペシャリスト人材は、狭い分野での仕事に特化したいわゆる“塩漬け君”状態になってしまっていて、創造性豊かに新たな価値創造を担えるかどうか大変心配です。
「塩漬け君」はどのような経緯で生まれたでしょうか。
まず、我が国においてスペシャリスト重視が進展した理由について考えてみましょう。
スペシャリスト化が進んだ理由は、以前金融業を中心に日本企業を襲っていた「ゼネラリストではアメリカに負けてしまう」という危機感です。私が勤めていたシンクタンクは、80年代後半アメリカに乗りこんだのですが、その際日米金融マンの専門性の差に愕然とした記憶があります。短期のローテーションと縦割り組織で育った人材では、海外の専門家にとても歯が立たないことに気がついたわけです。ほかの金融業界や他業界でも同様のことが起こっていたように思います。
そこで、若手を専門家として育成する動きが顕著になりました。これはこれで良かったことだと思います。
しかし、この動きが顕在化した直後に起きたのがバブルの崩壊です。80年代後半、バブルで浮かれる日本企業は若手を大量に採用しました。ところが数年後にバブルが崩壊、人を雇わなくなり、現場からどんどん人が減り、業務がひっ迫してくる中で、教育目的でのローテーションなどをやる余裕がなくなってしまったのですね。結果として、スペシャリストとして狭い業務範囲に押し込まれたまま、後輩も入らず入社以来十数年間同じ仕事を続け、その後いきなり管理職を任されるような状況が多発しました。89年に銀行に入社した大学の後輩が私に言った、「僕はキャリア採用されたと思ったのに、気がついたらノンキャリになっていました」という一言は、とても象徴的なセリフです。これが、“塩漬け君”が生まれた経緯です。
上記のことがあり、私は、日本企業のミドル層が疲弊しているように感じています。それが今の日本経済の弱さの原因の一つだと感じており、この問題意識に基づいて執筆したのが「中堅崩壊」という書籍です。