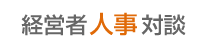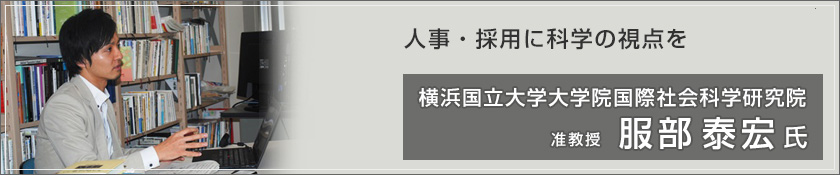日本ではこれまであまり重視されてこなかった経営学の一分野としての採用。
今回は、現在採用を科学的に検討する「採用学」の確立を進めている横浜国立大学大学院国際社会科学研究院 准教授 服部 泰宏 氏に、採用学とは何か、企業は採用時に何を重視すべきなのかについてお話を伺いました。
日本では採用への経営学的アプローチがほとんどされていない
樋口:
まずは服部先生の研究領域やなぜその研究を始めたのかを教えていただけますか。


大学でのゼミナールの様子
服部:
私はもともと採用に限らず、組織と人の関わり合い、とりわけ日本企業というものを研究していました。組織と個人の間には雇用契約のように文書化されたもの以外にも双方に対する暗黙の期待があります。たとえば、終身雇用がこれに当たります。これまで日本企業では暗黙の期待であってもある程度守られてきてきたわけですが、こうした暗黙の期待も含めてある種の契約とみなしても良いのではないかという考え方を「心理的契約」といいます。組織と個人の間の約束、と言い換えてもいいかもしれません。時代の変化に伴い、組織と個人の暗黙の約束の間には当然認識のずれが生じます。日本企業と個人の間にはどのような心理的契約があるのか、これを定量化、可視化して、時代の変化によって生じるずれはどういうところなのかを大学院生時代からずっと研究しており、書籍も出版しています。
このような研究を続ける中で、そもそも入口の段階で、組織と個人の間に、一方が他方に対して勝手な期待を膨らませ、それが入社後に問題として顕在化するというような、いわばボタンの掛け違えが起こっているケースが非常に多いことに気づきました。たとえば社員側の観点では「教育をもっとしてくれると言っていたのに・・・」といったことです。
このように会社への入口の時点に何か問題があるのではないかと考えたのが、私が採用に注目したきっかけです。
そこでいくつかの企業人事の方にお話しを伺ってみると、みなさん自分の会社独自の良い人材を採用しようとしているのですが、どうやら求めているものは結構似ているようなのです。
確かに似ていますね。
一言で表すと「人間力」ですよね。それをコミュニケーションと表したり、ある会社では対人関係能力と表したり、ネットワークと言い換えることもありますが、中身は非常に似ています。なぜこのようなことが起こるのだろうとさらに興味を惹かれました。また、私は学生を相手にしている教育者でもありますから、同じ大学の中でも内定をたくさんもらう学生とほとんどもらえない学生がいるのを目にします。これはまさに、多くの企業において同じような基準による採用が行われていることを意味するのではないでしょうか。これが良いことなのか、悪いことなのかは判断しかねますが、そもそも面白い現象だと思いました。
日本の中で文献を調べてみると、一部の教育社会学者などは、「学校教育と職業の世界とは、どのように接続されているか」「学校から仕事への移行はスムーズに行われているか」「そこでは格差が起こっていないか」という論の立て方をするわけです。
格差というのはどういうことでしょうか?
富めるものはますます富むようにという考え方や、親の年収が高いものは年収が高い仕事に就くとか、偏差値の高い大学に入学できた人は仕事の世界への移行においても有利な立場にある、といった議論は教育学特に教育社会学の重要なテーマになっています。一方で、企業側からすれば、ゆっくりじっくりと人材を育成する時間的余裕が無くなり、お金もかけられなくなるなかで、入口の時点で良い人をどう見抜くかという問題が切迫感を増しています。私は企業サイドから研究をしていますので、「就職学」だけではなく、「採用学」といったような経営学的なアプローチも大事なのではないかと思ったのです。調べてみると、日本では意外とこの観点からは研究されていないことに気づきました。一方英語で検索をかけると、ものすごい数の論文が出てきます。こうした背景もあって日本で採用学を研究しようと考えたのです。
私には非常に身近なお話ですが、先生以外の方がそこに興味を持たなかったのはなぜなのでしょうか。
いろいろな理由があるとは思うのですが、一つは日本企業が「優秀な人」ではなくて「育てれば伸びそうな人」を採用してきたことがあげられます。
そもそも採用時点でどんな仕事につかせるかが決まっていないのだから、採用時点で彼(女)らの能力を見ても仕方がない。むしろ育てれば伸びる人を採用したい。
では、育てれば伸びる人をどう見極めればいいか?ある程度の学習能力がある人を大学の偏差値を指標にして採用すればいいだろう。・・・これが、これまでの日本企業のロジックだったと思うのです。このような状況では研究者も特にそこを研究しようと思いませんし、企業もそもそもそういった要請を持っていなかったのです。
ニーズがなかったのですね。
もう一つは、研究に長い時間がかかる問題だからです。
仮に「優秀な人」を採用することを採用の成功と定義したとして、その人が「優秀な人」かどうかは入社してしばらくたたないとわかりません。
ですから日本企業が研究者とともにデータを開示して分析しなければならないのですが、そういったことをするインセンティブが企業側になかったのでしょう。
評価制度があっても実態の給与にはあまり差をつけておらず、それでもある程度社員を囲い込める組織では、いまだに先生のおっしゃるような終身雇用の概念を信じて組織を保っています。しかし、時代が変わり、一つの組織でずっと給料が上り、それが個人の幸せにつながる時代ではなくなってしまいました。そうすると、採用もさることながら、会社の存続意義と彼らの幸せをどうすれば最大化できるのか、経営者としては非常に悩ましいです。